 理由
理由
∴∴ A/Tサイド ∴∴
 理由
理由
∴∴ A/Tサイド ∴∴
|
プライベートが金に変わる。 ホストもホステスも差はない。性と、愛とか言う名の言葉遊びに飢えた孤独な輩に、ほんのちょっとばかりのプライベートを売り渡す。そうして暮らしているのが、ホストやホステスと呼ばれている人間なのだ。 いつ頃からか、突き上げるような性欲は無くなった。 代わりとばかり打ち寄せるのは、どうしようもない倦怠と惰性という名の日々。無為に過ぎて行く、繰り返される喧噪。騙し合いと傷の舐め合い。時折分からなくなる。 自分は何をしているのだろう? 何を求めてここにいる? ここにいる理由は? 「―――ってんだろ、よぉ!!」
「ったくよぉ。」
出来の悪い新人、何とか商品にしてやる為にもう暫くここにいる。
|
 続・理由
続・理由
∴∴∴ Hanakoサイド ∴∴∴
|
カリスマホスト。癒し系ホスト。盛り上げホスト。世の中にホストが一体何人居るのか知らないが、どんなホストでも、女との会話に中身はあまり無い。ノリと女の機嫌取り。それなりに客に合わせて話題を選ぶが、後はスキンシップぐらいだろう。 俺自身がホストを生業としているのに、そんな冷めた目を持つようになったのはいつからか。 指名が多くなればなるほど客が重なる。刃傷沙汰も何度かあった。 それでも俺はこの店でNo1と呼ばれる。 「…だから美里さーん。俺のことも構ってよ。」 「そうねぇ。光が最近冷たいし、亮君に乗り換えちゃおっかな。」 俺の背後から、わざとらしくそんな会話が聞こえる。俺の気を引くためだろう。無理もない。さっきボトルを入れてくれた恩も忘れて、さっさと次の客に呼ばれてしまったんだから。 「ふふ。光ったら薄情ものねぇ。」 「冴子ママ…。意地悪言うなよ。自分で無理矢理俺のこと呼んどいて。」 「だってぇ。あの子をちょっとからかってみたかったんですもの。」 悪びれもせずに俺の上得意の客がそう言った。接客のプロである銀座のママは、俺の立場をわざと悪くさせて喜んでる。 「今日は俺の顔を立ててよ。ママの本命のバーカウンターが空いてるよ。」 「光ちゃんも意地悪ね。いいわよ。本命のキッドにお相手してもらうから。」 ママはグラスを持って立ち上がった。カウンターまでついていき、ホスト席に背中を向ける椅子を引いた。大人しくそこに座ってくれたママにそっと耳打ちする。 「素直なママが一番可愛い。」 「私をからかうなんていい度胸じゃない。覚えておきなさいよ。」 完璧に塗られたマニキュアにデコピンを喰らった。 さて次は。 「お待たせ。」 「あら光。あの美人のお相手はもういいの?」 「悪かったよ。…妬いてくれた?」 亮の反対側の美里の隣に座り、少し体を傾けて下から見上げた。まだ手は握らない。 「亮、悪いがダンヒルをロックで2つ。」 美里がはっとしたようにこっちを見た。 聞き慣れない酒の名だったせいだろう。一瞬亮は戸惑ったが、美里の様子を見てすぐに立ち上がった。 「ほーい。」 さりげなく手を握る。 「美里と俺の思い出の酒だよ。」 かなり前に、美里がダンヒル好きの男に振られ、店にやってきたことがあった。彼女にとってはいい男だったんだろう。かなり落ち込んでいた。閉店間際になって事情を知った店長がこの酒を出してきた。 そのダンヒル好きの彼とお酒を飲みに行ったことはありますか? そうですか。このお酒の話題が出たことは? そうでしょうね。ダンヒルというブランドが好きでも、ダンヒルという名のお酒があることを知っている人は少ないものです。美里さんみたいに素敵な女性を選ばなかった彼なんかこのお酒を飲んで吹っ切ってください。 美里さんは笑顔の方が素敵ですよ。 それまで一生懸命涙を堪えていた美里が泣き出した。一口飲んでは泣いて、また一口飲んでは泣いての繰り返しだったが、気分は浮上していったようだった。 そしてその日、俺達2人は初めて体を繋げた。 それ以来、この酒を美里が注文したことも、俺が勧めることも一度もなかった。 目の前にダンヒルのグラスが2つ置かれ、わざと手を離した。 「俺を許せない?やっぱり亮に乗り換える?」 この酒で、俺のことも吹っ切る? 「………そんなわけ…ないじゃない。」 今度は美里の方から手を握ってきた。 閉店後。控え室で亮がしきりに俺にまとわりついてきた。 「やっぱすげーな光先輩。本気出すと、ああなのな。まじで感動したー。やっぱ奥の手ってのは最後まで出さないんだなー。」 いくらなんでも、全ての客にああいう奥の手があるはずもないのだが、それは秘密にしておこう。 「汚名返上出来たかな。今日の俺は『シケた先輩』だったんだろ。」 「今日の光先輩、前半と後半の冴え具合がダンチ!マジで!最高!」 もしかしたら新しい客がつくかもしれなかったというのに、亮はそのチャンスを俺に奪われたことも忘れ、俺にじゃれついてくる。 新人だからという理由だけじゃないだろう。ホストを商売と考えていない後輩が、ホストの俺の冷めた頭を熱くする。 面白い。 だが、そのままじゃ出来の悪いホストになっちまう。 俺がNo1になったテクをどんどん盗め。お前なら俺と全く違う最高級のホストになれるだろう。間違っても理由が無ければ冷めてしまうホストにはなるな。 「さて。冴子ママをいつまでも待たせるわけにいかないからな。お先に。」 「げ。あの性悪女まだいたのか。」 店長にすかさず殴られるのを横目に控え室を出た。 まずあの口の悪さから直させないとな。 また一つ、面白い理由が増えた。 |
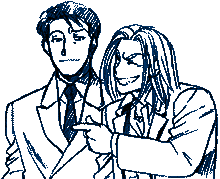 |
わっぱっぱ。久々にやったな、共作〜〜〜。
(続きだったので競作でなく共作と致しました) A/Tの分は、流石に思いつくまま書き殴りのあれじゃ何なので、加筆修正して、ちっとマシにしました。 そして。 Hanakoさん、有り難う御座いました。早速上げてしまいました。 と、はたと気付く。 大丈夫だったのだろうか、許可取ってねぇぞ。い、……良いよね良いよね?(媚び) |
| THE END | |